映画64(ロクヨン) 何を描きたかったのか?勝手に考察
映画64(ロクヨン)のラスト
遅れませながら、映画64(ロクヨン)を前後半一気に拝見した。
横山秀夫の小説が好きな私は、文庫版で小説をすでに読んでいた。詳細は記憶があいまいであるが、読後感は悪くなかった。しかし、今回の映画のラストはどうであろう。一言でいえば気にくわない。以前もSPECのラストを受け入れることができずそのテーマで書いた。その意味では二度目だろうか。
個人的には、この映画はお勧めしない。しかし小説は大いにお勧めする。

そして、最も腹が立つのが、後編のキャッチコピー「映画史に残る傑作の誕生 慟哭の結末を見逃すな」。個人的には「コピーに偽りあり」としか思えない。今からでも撤回していただきたい。この点について書いていきたい。小説・映画双方のラストネタをたぶん記載すると思うので、双方ともまだ見てない方は以下は、見ないで下さい。
注意 以下ネタバレしてます。
[cc id=19 title="記事内_広告"]
64(ロクヨン)について (横山作品というべきか)
横山作品の多くは、ミステリーに分類されるのかもしれない。しかし、その中で書かれているのは人間である。事件が起き、その謎を暴くという過程で、丁寧に登場人物の苦悩や喜びを描いてくれている。この点が、横山作品の好き嫌いのわかれるところでもあろう。
さて、小説64(ロクヨン)である。私は一言でいえば、傑作と言い切れる。希望しない職務と、それを受けざるを得ない家庭の事情を持つ主人公三上。組織の中の自分と職務と、自らの矜持との葛藤。サラリーマンの誰もが多かれ少なかれ感じている部分を持つ主人公が、警察の中の広報官という特殊な業務の視点から物語が進んでいく。小説を読んでいない方はぜひ読んでいただきたい作品である。
映画64(ロクヨン)のラストについて
さて、本題の映画版である。まず小説との一番の違いは、物語としての幕引き方法である。
ネタバレ注意
被害者の父雨宮が自分の耳だけをたよりに「電話での声」だけでつきとめた誘拐犯人を、県警は最終的に証拠不充分で釈放してしまう。松岡参事官は刑事部長に再度の聴取を要望するも聞き入れてもらえず、三上もその場で要望するが却下される。三上が一人で向かった雨宮家で、誘拐犯人の娘と遭遇する。娘を車に乗せた三上は、誘拐犯人に「小さな棺」の場所へ来るよう連絡。現れた誘拐犯と三上はもみ合いになるが、このこと自体が誘拐犯の自供を引き出す結果となり、誘拐犯は娘の目の前で犯人は逮捕され連行される。
もみ合いになった状況を、マスコミに報道された三上は(おそらく)警察を辞めることになる(失踪した娘さんを、これからは自分の足で探す、との発言あり)。ライバル二渡は「自らと刺し違えても、三上を守る」と言ったものの、新しい広報官として諏訪係長が記者クラブを仕切ることになった。
以上が、ラストの概略である。
父が連行される姿を見た娘の悲鳴。義憤にかられた三上の行動を報道し、退職に追い込むマスコミ。誘拐犯の娘を傷つけたと懺悔し、警察を去る三上。保身を図ったままの刑事部長や過去の捜査関係者。
唯一、引きこもった日吉が部屋から出てくることがよい結果だが、それ以外誰もが不幸な結末を迎える。これが許せない。
一体この映画で何を描きたかったのか。
[cc id=19 title="記事内_広告"]
マスコミの醜さ
この映画で描きたかったことは何か?
正直なところ映画を見て一番心に残ったのは「マスコミの醜さ」である。県警の対応にも不誠実な点はあるが、あまりにもマスコミの横暴が醜く描かれている。県警記者クラブと広報の関係もひどいが、マスコミ内の田舎担当と都会からの派遣組の間もひどい。作品中には「お前ら(県担当のマスコミ)が、ちゃんとサツをしつけないから、こうなるのだ!これだから田舎は(ダメだ)!」とやくざまがいの恫喝や行動が描かれている。証拠を見つけ出し、巨悪を打ちのめす、ようなジャーナリズムは全く存在しない。情報をよこせ、と高飛車な態度。まるでねつ造報道を繰り返す、現在のマスコミの実情を描き出しているように感じる。
匿名報道の理由
狂言疑い誘拐を県警は匿名報道で報道することを貫いている。広報室および捜査2課長は、そのためにマスコミからの攻めを受け続けることになる。「人としてそれ以上は(この時点で被害者である子供らの名前は)言えん」とトイレで数時間待ち続けた三上に対して、被害者の父の素性のみを松岡参事官は伝える。
小説では「今は被害者だが、加害者家族になる可能性を踏まえて」匿名報道を徹底していたことが、最後に明らかにされる。松岡参事官のロクヨンにかける執念が、誘拐事件はロクヨンの事件であると読み切り被害者匿名の指示をしていたのだ。マスコミの攻めを受けた広報担当者らの厳しい職務の裏に、人として組織としての大きなやさしさを描いている。厳しいミッションであったとしても、その真意が納得できれば頑張れるものだ。広報担当者らは厳しかったろうが、最後にすべての事情を明かされ、自分たちの仕事に大きな意味があったことを知る。組織はこうあってほしいものだ。
一方映画では、どうだ。最後まで保身に走った刑事部長の姿しか描いていない。保身に走るあまり匿名報道を行ったようにしか思えない。なんのために広報担当者らは体をはってマスコミと対峙したのか?上司の保身のためであったのか?それでは頑張ったことが報わない。
保身に憤りを感じた三上が、単独でロクヨン犯人と対峙し自供を引き出したすえに犯人逮捕となった。この過程での(結果的に)暴行を、マスコミは三上の暴行事件として報道し、警察官としての人生に引導を渡した結果となっている。
[cc id=19 title="記事内_広告"]
ひょっとして
ひょっとして、この作品の意図はそこにあるのかもしれない。
書きたかったことは、第一にマスコミの横暴。おまけで警察のだらしなさ。ではないだろうか。
映画で描かれるマスコミの態度はとにかくひどい。県警記者クラブは完全に立場が上であると勘違いをしている役どころであるし、繰り返しになるが三上の暴行は、結果的に誘拐犯逮捕に至っている状況で報道に値するのか疑問である。おそらくだが、この作品を見てマスコミを志望しようとする者はいないだろうと想像する。俳優陣も好感度が落ちたのではないだろうか。
いわゆるジャーナリズムというのは、どこに行ったのか。記者クラブでのんびりと警察と手を組む。その一方で事件の全体像からすれば些細なことである、三上の暴行をすっぱ抜く。都会からきた報道スタッフに文句を言われれば、警察に「もっとしっかりしてください」と要望する。他力本願もいいところである。これを仕事と勘違いしているのだろうか。
これがマスコミなのか?報道なのか?むしろ被害者であった雨宮と深く結びつき、その心情をもっと酌むことが報道のすべきことではないのか。権力たる警察が行わない被害者に寄り添っていくのか報道の在り方ではないのだろうか?群馬県という地域の中で最もかわいそうな人を忘れ、寄り添うこともできないくせに、一方では「知る権利」を主張するというマスコミという存在に対しての皮肉なのだろうか。
このマスコミの在り方に一石を投じたのであれば、私はこの作品を評価しよう。今現在のマスコミの不遜さを描き出している。今のマスコミの偏向(ねつ造)報道は、本当にひどいと心から感じている。
警察も、小説ではとてもかっこいい。小説でも誘拐犯が釈放されるのは同じだ。しかし、松岡参事官は言う「雨宮が容疑者を提示した。あとは俺たちの仕事だ」「1,000の証拠で埋め尽くす」「幸田メモは秘密の暴露に使えばよい」。
そう、過去とはいえ警察が秘匿した不祥事すらも、犯人特定の根拠として利用する。県警の大問題であっても逮捕のためには厭わない。これこそ組織がとるべき対応だ。(刑事部長だけは小説でも…)
それであれば様々な点に合点がいく。小説で大切にしてた多くの点をはぎ取ってまで、マスコミのひどさを訴えた映画であったと。「64-マスコミの横暴-」という副題にしてほしかった。
しかし、おそらくこの考えは過大評価だろう。単に原作とは異なる結果にしたかっただけで、小説に書かれている深いテーマを理解できずに映画化してしまった結果なのであろう。その意味では非常に残念な映画であった。
[cc id=20 title="インフィールド_広告"]
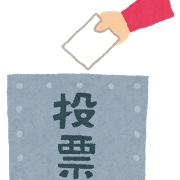





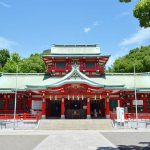

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません